なんか音楽アルバムの感想でも

Preprimer / Falcom Sound Team J.D.K. (90年 / Nihon Columbia)
ファルコムのゲーム曲にヨーロッパの風景を当て嵌めて、室内楽的アレンジを施したイメージアルバム。
特筆すべきは藤澤道夫氏のアレンジで、原曲を生かしつつ、決してうるさくなく、それでいてゆったりした時間を演出してくれる。
ファルコムはヒーリングアレンジのアルバムやクラシックにアレンジしたものを何枚もリリースしているが、これはその中でも出色の出来だと思う。
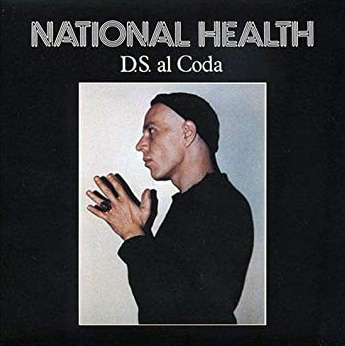
D.S. al Coda / National Health (82年 / Europa.)
81年に病で世を去ったキーボーディストのアラン・ゴウエンの追悼の為に、解散状態だったバンドのメンバーが結集して彼の曲を録音した追悼盤。
私的には1966年から続いたカンタベリーロックシーンの終着点であり、最後の残り火。
エルトン・ディーンやジミー・ヘイスティング、リチャード・シンクレア等もゲスト参加しているが、このアルバムのサウンドで印象的なのはデジタルシンセサイザーとエレドラの導入だろう。シモンズドラムのあの特徴的なパット音も名曲「Arriving Twice」の後ろで鳴っているシンセもまあ、言うなればThe・80年代なのだが、デジタルのそれは70年代の人力ローテクノロジーの世界からいきなり現代に来てしまった印象を受ける。とは言え、デイヴ・スチュワートのエレピはまごうことなく「あの音」だし、作曲家としてのゴウエンという人の、Gilgameshから続くパズルを組み合わせた様な曲も楽しい。

Live Around The World / Miles Davis (96年 / Warner Bros.)
カムバック後のマイルス・デイビス二枚目のライブアルバム(一枚目はWe Want Miles)。没後に出されたもので、88年からラストバンドの91年までの音源を収録。復帰後はライブこそ真骨頂という部分が多いので、こういった音源が出てくれることは嬉しい。やはり着目すべきはリッキー・ウェルマンのドラミングか。アル・フォスターは上手いが、どこかミスマッチ。ヴィンセント・ウィルバーンJr.は音色もポップな感じで悪くはないが、リズムパターンの引き出しが少なく、当時は演奏しているうちにテンポが遅れるという致命的な欠陥を抱えていて、求めていたサウンドに合うドラマーがいなかった中で、マイルス御大が発掘してきたのがこの御仁。(知る人ぞ知るGo-Goのチャック・ブラウン&ザ・ソウルサーチャーズ出身)聴いてて飽きないというか、ハットとバスドラのグルーヴ感が素晴らしい。リッキーは最後までバンドの屋台骨を支えることになる。
90-91年までのバンドメンバーは
Miles Davis (Trumpet / Keyboard)
Kenny Garret (Tenor Sax / Flute)
Joseph “Foley” McCreary (Lead Bass)
Richard Patterson (Bass)
Ricky Wellman (Drums)
Kei Akagi or Deron Johnson (Keyboard)
でおおよそ固定されつつあった。
マイルスは91年のラストバンドに於いて、従来までの雑多なサウンドから、ポップとファンクに振った先進的な方向に舵を切っており、固定されたバンドメンバーの演奏もかなりこなれたものになっていたので、願わくばこの後御大が2年くらい生きていれば、もっと多くの素晴らしい演奏が聴けたと思うのだが……。ちなみにシンディ・ローパーのカバー「Time After Time」はこのアルバムのテイクが一番好きかもしれない。伝説のクインテットや70年代の電化もいいが、この時期も充実していると思う。
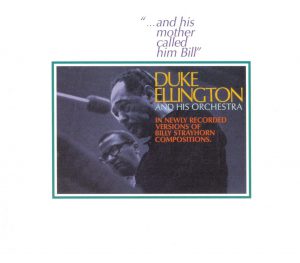
“…and his mother callled him Bill”/ Duke Ellington (67年 / BMG)
リリース同年に死去した作曲家ビリー・ストレイホーンのソング集。デューク・エリントンにとって、彼は作編曲の右腕的存在で、長年にわたり、エリントン楽団に多大な貢献した人物だった。手がけた曲を簡単に挙げると「Take a A Train」、「Satin Doll」「Raincheck」、「Chelsea Bridge」など、わかりやすく、洗練された中にどことなく可愛らしい主題を持っているもの、不思議な展開をしていく曲が多いのだが、このアルバムでは病苦の中、点滴を眺めながら作曲しエリントンに納めた最後の曲「Blood Count」。そしてジョニー・ホッジスの甘美なアルトサックスの冴える「Day-Dream」など、エリントン楽団も円熟期に入っていたのだが、素晴らしい演奏を聴かせてくれる。

Sound Of Science / 佐藤博 (86年 / ALFA Record)
「コスモ・エイジには耳で呼吸(イキ)する科学(ヤツ)もいる」というなんか、少年チャンピオンみたいな帯はともかく、傑作。
佐藤博という人は「Awakening」(82年)の時からLinn Drumなどの打ち込み機材を主体にサウンドを作っていたが、テクノロジーと機械的・非人間的なものを全面に出していたイギリスのニュー・ウェイブ系と違い、リズムトラックにしてもシーケンサーにしても、あくまでも人間的なノリとズレを主軸として、意図的に崩したりして、手弾きのスタジオセッションのサウンドに自然と融合させていたところに大きな違いがある。これは70年代のセッションミュージシャンに共通する項目でもあるのだが、ただ相当手間暇をかけて、凝っているあまり、正直どこまでが打ち込みで、どのパートを人が出しているものなのかが、この人のアルバムはクレジットを見ないと全くわからない(笑)。現代においても、かなり巧妙で自然なノリである。後のメロウなバラード曲が並びまくる日本のMr.AORと言っても過言ではない傑作「Future File」(87年)や、菅野よう子や本田雅人、パット・マステロットやリー・スクラ―まで居るキャリアハイの「AQUA」(88年)に比べると地味な感はあるが、冒頭の「Angelline」(再発版は角松敏生による12inch Disco MIXを収録や)をはじめとして、ダンサブルな曲が多い。あと、ファンキーなアレンジを施されたビートルズの「抱きしめたい」のカバーもあるし、でもこの人の本質はやはり、美しいメロディによるバラードかな。アルバム9曲の中で唯一日本語で歌われる「宇宙のエトランゼ」は都会から銀河のスペースコロニーまで飛翔していく感じで、メロディも歌詞も素晴らしい。
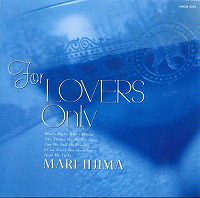
For Lovers Only / 飯島真理 (90年 / East West Japan)
カバーソング集。もう活動拠点をアメリカに移した後のアルバムだと思うが、選曲のセンスがいい。わずか5曲だが以下のような曲目になっている。
1.Who’s Right, Who’s Wrong (Pages)
2.The Thing We Do For Love (10cc)
3.Can We Still Be Friends (Todd Rundgren)
4.I Can Never Say Good-Bye (Original)
5.Hold Me Tight (The Beatles)
特筆すべきは1のPages(2nd のFuture Street収録)のカバーか。これは知る人ぞ知るグループだった。透明感がLAの夜じゃなくてバブリーな東京の夜なアレンジだが、丁寧な演奏だし、英語詩もしっかり歌っている。いいカバーだ。そしてメロウな10ccとToddの名曲と畳み掛けてくる。惜しむらくは単体単体の曲はシャッフルとかバラで聴く分にはとてもいいんだが、アルバムとして通して聴くとアレンジがどうも一本気で単調なんだよな。企画ものだからしょうがない点でもあるが。ただこのセンスの良さは非常に買う。

Really / Fifth Avenue Band (90年 / Pony Canion)
あの伝説の1stから20年近くの時を経て暫定的に復活した際のFABのアルバム。実際 は日本のレコード会社側が企画したアルバムのようで、各々作曲し、外部ミュージシャンと録った曲を持ち込む体裁を取っている。クレジットにはAll Vocal by FABとなっているので、多分コーラス等はメンバーが担当しているのだろう。(ピーター・ゴールウェイのライナーノーツによれば、このアルバムを出す前の、日本でのソロツアーが大いに刺激になったという)。しかし音はデジタルシンセと打ち込みのリズムボックス、あの80年代特有の大きめのドラム音、コーラスがかかりまくったギターサウンドなどが多く取り入れられた正に都会的AORサウンドで、1stのアコースティックで洒落たソフトロックの世界やオハイオ・ノックスの音からかなり逸脱した世界でかなり驚いた。だが、聞き込んでみて、なんというかやっぱFABのアルバムだなと思えるのはそういった 90年当時流行の音に合わせながらも、どこか明るく洒脱というか、出てくる音が時には、ボサノバであったり、ジャジーなギターフレーズであったり、60年代のソフトロック的なコーラスワークを忘れていなかったりするところが実に良い。私的に90年代以降のシティポップ、いわゆる都会的サウンドとして、好み のアルバムを一枚挙げるならば、スティーリー・ダンの再始動アルバム「Two Against Nature」よりこちらを推したい。

POV / Utopia (85年 / Passport)
ラストアルバム。ベアズヴィル・レコードを離れ、前作同様パスポートレーベルからのリリースだが、余りにもマイナーなレコードレーベルの為に宣伝も上手く行かなかった上にチャートでも振るわず、このセッションに於いて、ドラムマシンを作品に導入したいウィリー・ウィルコックス(Dr)に対し、トッド・ラングレンが激しく反発していたなど、メンバー間の確執が表面化しており、このアルバムを 最後にバンドは解散してしまった(92年に一時的に再結成)。そんな複雑な背景をよそにすれば、本作はカシム・サルトン(B)が「あの作品は供給が需要を 上回ってしまっていた」というぐらいに、トッドやユートピアの作品の中でも五指に入る超絶ポップアルバムである。ニューウェーヴを感じさせながらも、ユートピアお得意のコーラスワークが冴える疾走ナンバーZen Machineや、ウィリー・ウィルコックス作で、ウィリーとしては本当はトッドがこういった曲を作って歌って欲しかったという、トッド風バラード Mated。カシム作の軽快なパワーポップ、Wild Life。ロジャー・パウエルのシンセサイザーがEL&Powellやエイジアとの親和性を感じさせるMore Light等、演奏の上手さも含めてどれも珠玉の出来。2011年のEsoteric Reccordからの再発版では86年のコンピレーションアルバム「Trivia」等から三曲追加。こちらの方はトッドの路線が後のアルバム「2nd Wind」に続いていく事を感じさせるFix Your Gazeが良い。

アワー・コネクション / いしだあゆみ&ティン・パン・アレー・ファミリー(77年 / Columbia)
演技派女優とティンパン・アレーという異色の組み合わせ。参加メンバーは松任谷正隆抜きのティンパン・アレー(細野晴臣、鈴木茂、林立夫)に、ギターに吉川忠英。管がジェイク.H.コンセプション。パーカッションに浜口茂外也。コーラスで吉田美奈子、山下達郎。鍵盤に矢野顕子、岡田徹、佐藤博、果ては羽田健太郎という名前だけ見ていても恐ろしいメンバーが集結している。サウンドはあくまで歌謡曲ではあるのだが、かといって、古くさいかというと全くそうではなくて、確かに曲全体に70年代の香りはあるものの、いしだあゆみの声の湿っぽさと、ティンパンの都会的センスが絶妙に合っている。あとは全編、橋本淳の詩がきちんとした一つの世界を作っているところが素晴らしい。ここでのいしだあゆみは仕事に疲れた都会の女であったり、男を待つ寂しい女であったりするのだが、ラストの「バイバイジェット」で、想っていた彼は羽田から飛行機で国際線で遠くに。でもいしだ自身は少しばかり憂いを持ちながらも「バイバイジェット…」と吹っ切れたように明るくつぶやきながら去っていく。そのバイバイはやや騒がしい80年代を前にした70年代へのさよならのようにも聞こえる。ティン・パンの紡ぎ出す当時の東京の情景と実にマッチしている昭和の名盤と云って良いだろう。

イースIV -The Dawn Of Ys- (93年 / Hudson)
厳密に言うと、これはアルバムではない。日本ファルコムが委託し、ハドソンが開発・発売したPCエンジンのソフトで、懐かしのCD-DA方式(一昔前のいやらしいPCゲームでよくあったやつね)の為に、ゲーム内で流れる楽曲がCDプレイヤーで再生できるのだ。アレンジャーは前作、前々作同様、米光亮が担当。「溶岩地帯 ~ エルディールにくちづけを」、「太陽の神殿」、「Theme Of Adoru 1993」、「灼熱の炎の中で」、「セルセタの樹海」等、曲に良い物が揃っているというのも大きい。「道化師の誘い」なんかのベースのグルーヴは生演奏でしか出なかったと思うし、あとは1の「Tower of The Shadow of Death」の大胆なアレンジは特筆すべきだろうと思う。しかし、まあ、PCエンジンというハード自体が超高価だったが、このゲーム自体も池田秀一や鶴ひろみが喋るわ、アニメーション原画監修は芦田豊雄だったり、ローランドのRSSという当時最新の立体音響システムを使っていたりと、かなり金のかかった作りになっていて、実にうん。バブルだ。あとイースIVというと必ず話題になるのがイングヴェイ・マルムスティーン&ライジングフォースの「Far Beyond The Sun」まんまの「偉大なるアレ」であるが、やはりファルコムとしては無かったことにしたいのか、iTunesストア等でダウンロード販売されている「イースIV パーフェクトコレクション」からも存在が抹消されている。
j∬-●3●)<…
